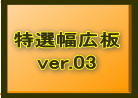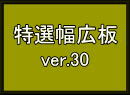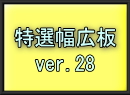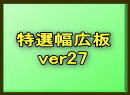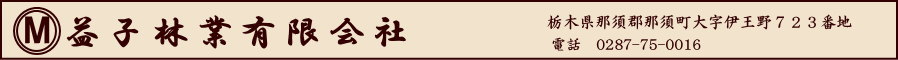

益子林業のブログ
-
幅広一枚板 その2 2025.07.30
-
とちぎ八溝杉を扱う益子林業です。
益子林業では、テーブルに使われる幅800㎜以上の幅広一枚板よりもカウンターなどに使われる幅450㎜程度の幅広一枚板の方がよく売れます。
このカウンター用は粗挽き寸法で厚み55㎜に製材しています。
在庫し始めた頃は厚み50㎜でしたが、予想以上に反りが大きいので途中から55㎜に変えました。
反りを防ぐためにさらに厚くすれば良いかもしれませんが、狂いを取って40㎜~45㎜で使う方が多いので原板厚55㎜としました。
これを作り始めた平成25年頃は、1年間ほど天然乾燥すれば使えるレベルになると思っていましたが、実際納品したお客様に聞くと、狂い(反り)を取ってもまた狂って(反って)しまうとの声があり、現在は天然乾燥3年以上が販売可能レベルとして決めています。
このカウンター用の幅広一枚板もUNDER8ではありません。
人工乾燥で低含水率にすると干割れが発生してしまうからです。
天然乾燥(倉庫内)で平衡含水率にするには55㎜の厚みで約3年かかると思います。
それでも環境が変わり、住宅のカンターとして施工するとさらに乾燥は進むでしょう。
ですから、天然乾燥で出来る限りの低含水率まで下げる必要があると考えています。
話は少し変わって、耳付きの幅広板の寸法表示のお話をさせて頂きます。
通常の木材製品は、過去のものを含めJAS規格に則っているものが多いのですが、この耳付き板には明確な寸法表示の基準が無いようです。
耳付き板の殆どは、末口と元口では幅の広さが違います。
ではどちらの幅で表記するのが正しいのでしょう。
末口で計らないと耳を落とした時に狙った幅が取れなくなりますから、買う方の立場になれば末口にしてほしいでしょう。
しかし、売る方にしてみれば元口の方が材積が多くなるので㎥単価で売る場合は儲かります。
中には、間を取って中径表示にしている製材所もあります。
日本国の常識に照らし合わせると、末口表示しかあり得ないと思うのですが、これをお読みの皆様はどう思われますか?
私は、末口表示にして、それに見合った㎥単価で販売すれば誰も損をしないと思っています。
いずれにしても世の中に流通している耳付き幅広板は中径表示(板の中間の幅で計測)が多いので、購入する際はご注意ください。
ちなみに、益子林業の耳付き幅広板は全て”末口の耳の内側”の寸法で表記してあります。
時間があるときに、ホームページの特選幅広板のボタンをクリックしてみてください。
(このページ右側に幅広板ページへのリンクボタンがあります。)