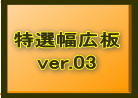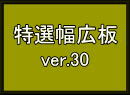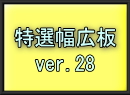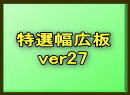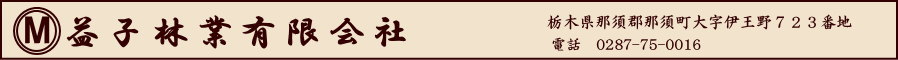

益子林業のブログ
-
幅広一枚板 その1の続き 2025.07.28
-
とちぎ八溝材を扱う益子林業です。今回は前回ブログの続き「幅広一枚板」の価値・POINT6から始めます。
point6の乾燥度合いは、まさにpoint5素性(狂いの度合い・狂う可能性)の見極めの難しいところを明らかにする大切な要素です。
しかし、厚み75㎜×幅800㎜の材になると、人工乾燥はとても危険です。
乾燥に失敗すると何万円もの価値のある製品が無駄になるのですから、少なくとも私にはそんな勇気はありません。
ということで、この手の一枚板は天然乾燥をするわけですが、ちなみに杉の厚み75㎜×幅800㎜のグリーン材をテーブルの天板として使用する場合、私は5年以上の天然乾燥が必要だと思っています。
天然乾燥でも早く乾かそうとして風通しの良い場所に置くと材面が割れる可能性が高くなります。
ですから、カビが発生しない程度の日陰で、そこそこ空気が循環する環境で天然乾燥を行います。ということで、やはり5年ぐらいは経たないとその後の変形が心配です。
point7の材長は、長いほど㎥単価は高くなります。
樹齢300年~500年の丸太となると、いわゆる人工林には殆ど有りません。
市場に出回る原木のほとんどは、どこぞのお屋敷の敷地に立っていたり、神社やお寺に立っていた場合が多いので、枝下の長さが意外と短かったり、肝心な元玉にはうろ(樹洞)が入っていたりと長い原木(例えば6m材など)はさらに希少性が高くなります。
加えて、運ぶにも製材するにも乾燥するにも長い程取り扱いが難しくなります。
point8の厚みは、単に材積が上がるため単価が高くなるということです。しかし、かといって幅広一枚板の場合は、厚みが薄いとそれだけ狂う(反り、捻じれ)確率が上がることを押さえておく必要があります。
最近の傾向として、デザイン性を優先して薄い材を求められることが多いです。
屋根も薄くしたい、枠も薄くしたい、カウンターも薄くしたいなどなど。
確かにデザインはかなり重要ですが、強度が低下したり、材木に変形が生じてしまっては元も子もないでしょうから、厚みと変形の関係は押さえておいて頂いた方がいいでしょうね。
厚みの話のついでに、厚みと材積の関係をお話しすると、幅が1㎜増した時と厚みが1㎜増したときの材積の増え方はまるで違います。それは当然だろうと思われるかもしれませんが、肌感覚(実感)としてご存じの方は意外と少ないようです。
実際にあった話ですが、ある工務店さんに羽目板の見積もりを提出したところ、「なんで益子さんはこんなに高いんだ」と返答があったので、よくよく話を聴いてみると、よそ様の見積もりは厚みが9㎜で私の見積もりは12㎜だったのです。
幅が一緒でも厚みが30%以上も違えば、比較すること自体滑稽なことですが、厚みと材積の関係を知らないとこういうことになります。
【幅広一枚板その2に続く】