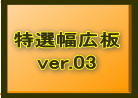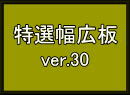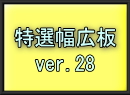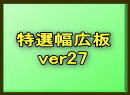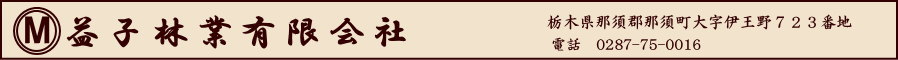

益子林業のブログ
-
甲羅板の外壁材 2025.10.30
-
とちぎ八溝杉を製材・販売する益子林業です。
日頃よりお仕事をご依頼頂いている工務店様から外壁材のご注文を頂きました。
改修工事で、既存の外壁が杉の甲羅板で造ってあり、同じような材料が欲しいとのことです。
そもそも甲羅板とは背板とも呼ばれていますが、丸太の丸みがそのまま残っている板のことです。
本当は既存の外壁の写真でもあれば分かりやすいのですが、今回は電話で担当者が見たイメージでご注文を頂きました。
この注文の頂き方から判断して、それほどシビアな品質を求めていないことが伺え、「益子林業に任せておけば上手くやるだろう」というように感じられました。
また、最終的な仕上げは大工さんがやってくれるとの心強いお言葉を頂いたので、皮もリングバーカーで剥いたもので可、少々の傷も可という点を確認してお受けしました。
那須の別荘地を控える立地で営業していると、この手の注文のご相談を頂くことは、たまにありますが、難しいのはどの程度の品質が求められているかを把握することです。
よくあるのは、「製材の落しだから簡単なんでしょ!」と言うものです。
製材のことを知らないと簡単に考えてしまうのも仕方ないのでしょうが、通常の落し(甲羅板)は末よりも元の方が厚く、幅広になります。丸太によっては元は末の倍以上の厚み、幅になります。
このままではとても外壁材としては使えないので、幅詰めをするわけですが、末と元の厚みが倍の甲羅板を貼ったときをイメージして頂きたいのです。
イメージが出来た上でのご注文ならば問題ないのですが、ややもすると「こうなるとは思わなかった」となります。なので、求められる品質を理解できない場合には、末と元と中間の厚みをなるべく等しくするように製材します。

通常、製材するときには”丸太の芯”と”鋸の通り道”が平行になるように木取りしますが、鴨居のように柾目を通したい場合には、”丸太の表面”と”鋸の通り道”が平行になるように木取ります。
この木取の仕方を「鴨居挽き」と呼んでいますが、鴨居挽きで面倒なのは、丸太の両サイドを落し終わった時点で、残ったタイコの部分が台形になってしまうことです。この残りの部分から良い製品を取ろうとすると、台形のタイコを芯を中心に長方形に挽き直さなければなりません。
つまり鴨居挽きをすると、タイコの修正挽きの分だけ手間(コスト)がかかります。なので、柾目が通った鴨居は柾目の流れた(曲がった)それよりも値段が高いわけです。それ以外にも、直材でなければ柾目は通りませんので、素性の良い丸太をさらに手間をかけて初めて柾目の通った鴨居は出来上がります。
実は、甲羅板を幅詰めして末と元と中間の厚みを揃えようとするには、直材の丸太で、鴨居挽きすることが必要になります。このことを知って注文される方とはまだ出会ったことがありません(笑)。製材している者にとっては当たり前の理屈ですが、経験していないと簡単に考えてしまうのです。
なので、「製材の落としなので簡単でしょ!」となってしまうわけですね(笑笑)。
何はともあれ、ご注文の甲羅板



長さ4000㎜ 幅120㎜ 幅詰め面の厚み30㎜~35㎜ 30枚のご注文の製品が完成し出荷の準備が整いました。
例によって、こだわりすぎて少々コストを掛け過ぎましたが、それはご理解頂かなくても仕上がりが奇麗になれば十分です。
あとは腕利きの頼もしい大工さんが表面をきれいに仕上げて頂けるものと思います。
今回も益子林業をご用命頂きまして、誠にありがとうございました。
- 【次の記事へ】 【前の記事へ】